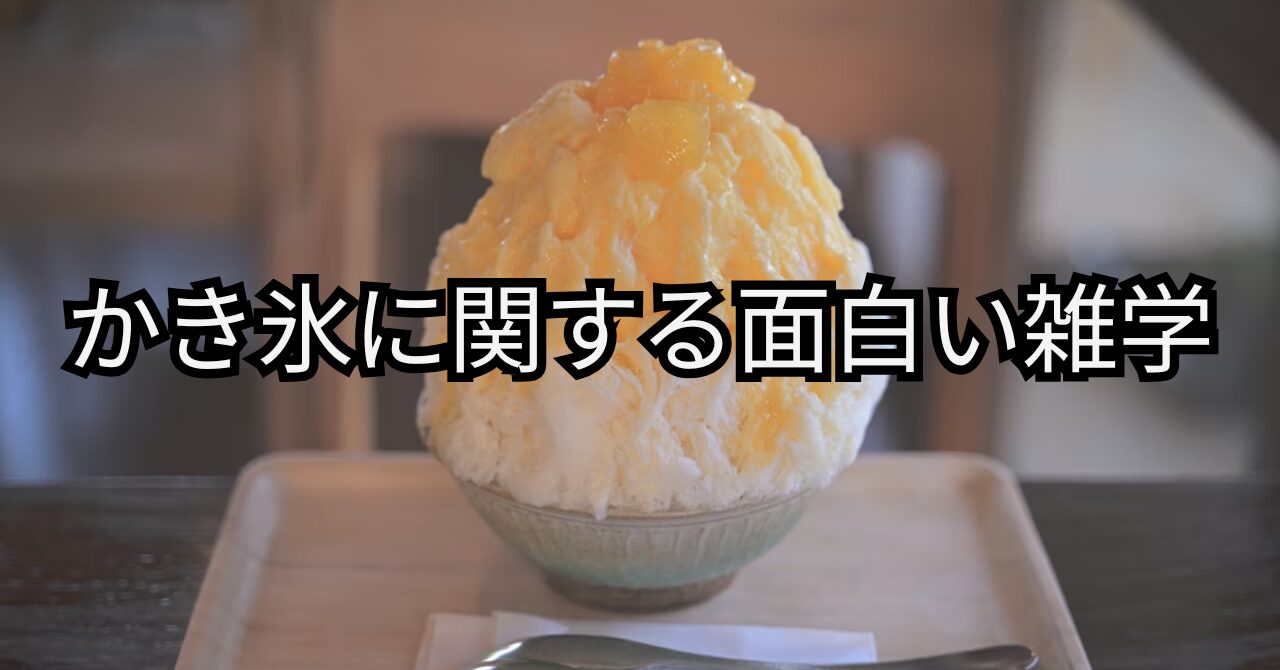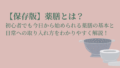暑い夏の風物詩といえば、やっぱり「かき氷」。ふわふわの氷に色とりどりのシロップをかけて楽しむこのスイーツには、実はたくさんの面白い雑学や奥深い歴史が隠されています。ただの涼しさを楽しむ食べ物と思われがちなかき氷ですが、そのルーツや進化、文化的な背景には驚きのエピソードが満載です。今回は、そんな「かき氷に関する面白い雑学」をたっぷりとご紹介します。
かき氷の起源は平安時代!日本最古のかき氷記録とは?
かき氷の歴史は意外にも古く、平安時代までさかのぼります。実は『枕草子』の中に、氷に甘い蜜をかけて食べる記述があるのです。これは現在のかき氷のルーツとされており、当時は「削り氷(けずりひ)」と呼ばれていました。
この頃の氷は自然の氷を冬に保存していたもので、とても貴重なものでした。そのため、かき氷は宮中の限られた貴族しか口にできない、まさに“幻のスイーツ”だったのです。現代のように誰でも気軽に楽しめる時代がくるとは、当時の人々も夢にも思わなかったことでしょう。
昔の氷は夏まで保存していた!氷室(ひむろ)の役割
電気冷蔵庫のない時代、人々はどのように氷を夏まで保存していたのでしょうか?その答えが「氷室(ひむろ)」です。氷室とは、冬に凍らせた天然の氷を貯蔵し、夏まで保管しておくための施設です。
氷室は主に山間部や涼しい場所に作られ、天然の断熱素材であるワラや木の葉で覆われていました。湿度や日光を避ける工夫もされており、驚くべきことに、数ヶ月も氷を溶かさずに保存できたといいます。この氷室の存在が、夏にかき氷を食べる文化を生んだともいえるでしょう。
明治時代のかき氷は超高級!値段に驚き
庶民がかき氷を食べられるようになったのは、明治時代以降です。とはいえ、当初はまだまだ高級品でした。明治27年、横浜に開店した日本初の「かき氷屋」では、1杯のかき氷がなんと「金1銭」だったと記録されています。
当時の労働者の日当が10〜15銭ほどだったことを考えると、かき氷1杯は現在でいえば1000円以上の感覚です。それでも、真夏の涼を求めて多くの人が行列を作ったそうです。冷房のない時代、かき氷はとても貴重な“涼”だったのです。
シロップの定番「イチゴ味」に果汁は入っていない?
かき氷といえば「イチゴシロップ」が定番ですが、実は多くのイチゴシロップには果汁が一切含まれていません。なぜなら、あの鮮やかな赤色と甘酸っぱさは、香料と着色料によって再現されているからです。
これはイチゴに限った話ではなく、「メロン」や「ブルーハワイ」なども同様です。つまり、かき氷のシロップの多くは“味のイメージ”で作られており、実際の果物とはまったく違うものなのです。
このことを知っていても、やっぱりイチゴやブルーハワイのシロップを見るとワクワクしてしまいますよね。視覚と味覚の不思議なトリックが、かき氷の魅力の一部といえるでしょう。
「ブルーハワイ」は日本生まれだった!
かき氷のシロップでおなじみの「ブルーハワイ」。このトロピカルな名前から、てっきりハワイ生まれだと思っている人も多いのではないでしょうか?実はこのブルーハワイ、完全なる日本発祥の味なのです。
ブルーハワイのルーツは、昭和40年代に日本で生まれた清涼飲料水のフレーバーです。ハワイをイメージした青色の飲み物やシロップとして親しまれるようになり、やがてかき氷の定番シロップとして定着しました。
つまり「ブルーハワイ=ハワイの味」というのは、あくまでイメージ戦略だったというわけです。このように、かき氷の世界にはユニークな発明やアイデアがたくさん詰まっているのです。
ふわふわ氷の秘密は刃の角度と温度管理
最近では“ふわっふわ”の口溶けが自慢の「進化系かき氷」が人気ですが、あの食感には秘密があります。ポイントは「氷を削る刃の角度」と「氷の温度」です。
まず、ふわふわの氷を作るには、氷を“冷やしすぎない”ことが重要です。氷がキンキンに冷えていると削る際に硬くなり、ジャリジャリした食感になってしまいます。逆に、氷の温度がやや高めだと、柔らかく削れてフワフワになります。
さらに、削る刃の角度を微調整することで、氷の断面が滑らかになり、口に入れた瞬間にスッと溶ける繊細な舌触りが生まれるのです。この繊細な職人技が、“究極のかき氷”を生む秘密です。
地域によって呼び方が違う?「けずり氷」「氷水」「アイス」
かき氷には地域ごとにさまざまな呼び方があることをご存じでしょうか?たとえば関西地方では、かき氷のことを「氷水(こおりみず)」と呼ぶことがあります。これは昔、氷に甘い蜜をかけていた名残です。
また、九州の一部地域では「アイス」と呼ぶこともあり、これは氷菓全体を指す言葉として使われることもあります。「けずり氷」という表現も古くから使われており、地域ごとの文化や言語の違いが垣間見えます。
こうした呼び方の違いを知ると、旅先でのかき氷選びも一層楽しくなりますね。
世界のかき氷事情も多彩!台湾やハワイの人気スタイル
かき氷は日本だけのものではありません。世界中に似たような氷のスイーツが存在しています。たとえば、台湾の「雪花冰(シュエファービン)」はミルク氷を削ったもので、フルーツやタピオカなどがたっぷりとトッピングされています。
ハワイでは「シェイブアイス」が定番です。色鮮やかなシロップを使い、レインボーカラーに仕上げられたその見た目は、まさに南国のスイーツといえるでしょう。
韓国では「ピンス」が有名で、ふわふわの氷の上にあんこやフルーツ、アイスクリームを乗せた豪華なスタイルです。日本のかき氷とはまた違った楽しみ方ができるのが、世界の氷スイーツの魅力です。
かき氷の祭典も存在!全国の名店が集うイベントとは?
日本では近年、「かき氷」をテーマにしたイベントやフェスが各地で開催されています。その中でも有名なのが「かき氷コレクション」や「かき氷博覧会」です。
これらのイベントでは、全国から人気店や話題のかき氷職人が集まり、それぞれオリジナリティあふれるメニューを提供します。例えば、抹茶や黒蜜、果物を贅沢に使った“スイーツ系かき氷”から、和風・エスニック風の変わり種まで多彩なラインナップが登場します。
普段なかなか出会えない遠方の名店の味を一度に楽しめるのも、こうしたイベントの醍醐味です。
まとめ:かき氷は夏の風物詩以上の魅力を秘めたスイーツ
かき氷は、ただの夏の涼をとるための食べ物ではありません。千年以上にわたる歴史、技術、文化、そして世界中に広がる多様性に支えられた、奥深いスイーツなのです。
「イチゴシロップに果汁がない」「ブルーハワイは日本生まれ」「ふわふわ氷の秘密は温度管理」など、知れば知るほど楽しくなる雑学が詰まっています。次にかき氷を食べるときは、ぜひ今回ご紹介した雑学を思い出してみてください。いつもより一層、おいしく感じられることでしょう。